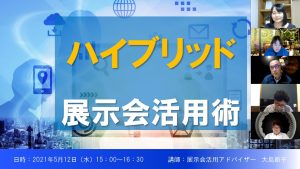展活セミナー2021 3講レポ
おはようございます^^
中小企業向け販路開拓コンサルタント・展示会活用アドバイザーの大島節子です。
大阪に帰ってきました。気持ちの良い五月晴れ。そんな大阪から今日も展活タイムズをお届けします。
チラシを作りながらコンセプトをブラッシュアップ
5月13日はあいち産業振興機構さん主催の展活セミナー3講でした。

3講は今年も「ウェブ再生塾」講師の村上肇さんの講演からスタート。
・ビジネスの本質とは?
・ウェブと展示会の親和性
・諸行無常
について、ご講演いただきました。
恐れ多くも展活セミナーはウェブ再生塾の姉妹講座と位置付けていただいています。ウェブと展示会は中小企業の販路開拓の両輪です。単体ではなくそれぞれの良さを活かして活用することで更なる効果を出すことができます。展活セミナーも6期目となり、よい感じで相乗効果を出していらっしゃる事例も多数出てきました。

本編では参加企業さんたちの進捗状況を発表いただき、どうすればもっと伝わる表現になるか、チラシラフ案を軸にディスカッションを深めていきます。講座も3講目ということでお互いの出展商品について随分わかってきたので、具体的で的確な指摘が交わされるようになってきました。
「お客さまは何に困っていて、自社はそのお困りごとに対して何を提供できるのか」。この部分の言語化さえできれば展活セミナーの役割は9割方達成です。残りの1割が諸々の展示会テクニックです。肝になる“言語化”の部分をもうひと頑張りしましょうね!

3講の締めは犬山印刷、宮島さんのプレゼン。毎年、展活セミナー参加企業のチラシとブース用タペストリー等のデザインと制作の受け皿になっていただいています。過去6年分の事例があるので、信頼感がますます増してきており、展活セミナーの頼れるパートナーです。「ブース作りの不安が解消されて良かったです」という感想をいただきました。
4講ではチラシ案をブースに展開、5講では問題解決型プレゼンテーション動画に展開する方法をお伝えいたします。出展を迷っていらっしゃった方たちも覚悟を決められたので、今年の秋には問題解決型ブースの名作がまた多数誕生します。展示会が無事開催さえされれば!(笑)今年のメッセナゴヤでは各ブースから展活チャンネルのライブ配信を考えています。私もずっとメッセナゴヤに行ったっきりになるかも。お楽しみに~!
まとめ
今朝の展活タイムズはあいち展活セミナー3講のレポでした。
今日もお読みいただきありがとうございます。