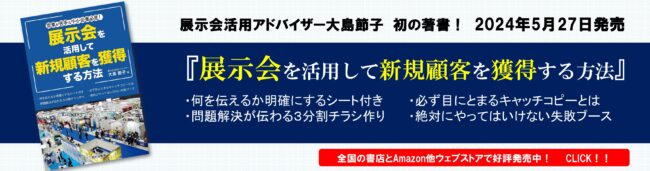なぜIT・DX系展示会は呼び込みが強引なのか
おはようございます^^
自社の問題解決力を見える化し展示会を成功に導く、展示会活用アドバイザーの大島節子です。
暑いですね~。雨も多いので湿気もなかなか。そんな早朝の大阪から今朝も展活タイムズをお届けします。
IT・DX展示会の強引な客引き、理由を考えてみた
5月21日(水)~23日(金)インテックス大阪にてDX総合EXPO2025springが開催されています。そこでつくづく感じたことがあるので今日はそのことについて書いていきます。
展示会によく足を運ばれる方、「IT系」や「DX系」と名の付く展示会で、こんな経験はありませんか? ブースの前を歩いていると四方八方からと声をかけられ、時には、数m真横を歩いて声をかけられ続け「ここどこ?夜の繁華街?」と錯覚することも…(笑)。

もちろん、会場に活気があるのは素晴らしいことですし、出展社さんの熱意の表れだとも思います。でも、「うーん、ちょっと強引すぎるかな…?」と感じてしまうこと、正直ありますよ。 特にこのIT・DX系の展示会で、そうした強引な客引きが目立つのはなぜなのでしょうか? 今日は、私なりにその理由をいくつか考察してみたいと思います。
考察1:イケイケドンドン!ベンチャー企業の社風
まず一つ目に考えられるのは、IT・DX業界には、他の業界と比べて短い社歴で急成長してきたベンチャー企業やスタートアップが多いという点です。
・「とにかく成長第一」「スピードこそ命」という、いわゆるイケイケケドンドンな社風であることが多いように感じます。
・既存のやり方や常識にとらわれず、アグレッシブに市場シェアを獲得し、業界のトップを目指す!という強いエネルギーに満ち溢れています。
・そのため、展示会という絶好の機会も、「お客様が来るのを待つ」という受け身の姿勢ではなく、積極的に「狩り」にいく!とばかりに、一人でも多くの来場者に声をかけ、自社のソリューションを伝えようとするのではないでしょうか。
その結果、ブーススタッフの方々の振る舞いも自然とエネルギッシュになり、時に私たち来場者から見ると「強引だな」と感じられるほどの積極性につながっているのかもしれませんね。
考察2:課せられた「数値目標」
次に考えられるのが、ブースに立つスタッフの方々が、会社からかなり厳しい「数値目標」を課せられているのではないか、ということです。
・会期中に名刺〇〇枚以上獲得
・製品デモンストレーションへの参加者〇〇人達成
・具体的な商談アポイント〇〇件獲得
この目標が、結果として「とにかく一人でも多くの来場者情報を獲得しなければ」という行動に繋がり、時にはそれが私たちから見ると強引な声かけや引き込みに見えてしまう…そんな背景もあるのではないかと推察します。
考察3:MAツールへの自信?「まずはリスト化」の戦略
そして三つ目の考察として、近年のマーケティングオートメーション(MA)ツールの目覚ましい進化と普及が、このアグレッシブなスタイルに影響を与えているのではないか、という視点です。
・たとえ展示会ブースで、少々強引な形で獲得した名刺情報(リード)であっても、心配無用
・ その後のMAツールを使った丁寧なナーチャリング(顧客育成)で、興味関心の度合いを見極め、最終的には有効な見込み客へと育てていける自信がある
・だから、展示会ではまず“質より量”で多くの接点を持ち、とにかくたくさんの情報を集めて、我々のマーケティングの“入り口”に乗せることが何よりも重要
「あとはウチのMAが何とかしてくれる」という、ある種の自信と割り切りが、展示会での積極的(時に強引な)なリード獲得活動を後押ししている可能性も考えられますね。
考察4:「形がない」からこそ「声」で勝負?
そして、もう一つ、IT・DX系の展示会特有の事情として考えられるのが、扱っている製品やサービスが「形のないもの」であるケースが多いということです。
例えば、ソフトウェア、クラウドサービス、業務改善ソリューション…これらは、実際に手に取って動かせる機械や、見た目にインパクトのある製品とは異なり、ブースにただ置いただけでは、その価値や魅力が一瞬では伝わりにくいという特性があります。
つまり、来場者の目を引くような「アイキャッチになる展示物」を物理的に作りにくい。そうなると、どうやって来場者に足を止めてもらうか? 必然的に、「声かけ」による直接的なアプローチ、つまり「客引き」の重要度が増してくるのではないでしょうか。
「弊社のこのシステムを使えば、御社の業務効率が劇的に改善しますよ」 「今、お困りの〇〇を解決できるソリューションがこちらです」 と、言葉で積極的に働きかけないと、そもそも何を提供している会社なのかすら理解してもらえない、という事情があるのかもしれません。 「形がない」からこそ、まずは声で興味を引き、話を聞いてもらうステージに立たなければならない。それが、IT・DX系展示会の客引きが、より積極的にならざるを得ない理由の一つではないかと感じるのです。
来場者としては…
とはいえ、私たち来場者側からすると、あまりにも強引な客引きは、やはり少し引いてしまったり、じっくりと製品やサービスを見たい気持ちを削いでしまったりすることもありますよね。

出展社にとっては、限られた会期中に最大の成果を出すための積極性と、来場者に与えるイメージバランスをどう取るか、というのは常に難しい舵取りなのだろうと感じます。
まとめ
今回挙げた4つの考察「ベンチャー企業の社風、厳しい数値目標、MAツールへの自信、そして形のない製品ゆえの難しさ」は、あくまで私個人の長年の展示会ウォッチャーとしての推察です。きっと、他にも様々な理由が絡み合っているのでしょう。
そして全てのIT・DX系展示会が強引なわけではないのです。今年のはじめに見た「AI博覧会」などはとても品の良い空気感の展示会でした。展示会によっても色が違います。
展示会のスタイルはきっとこれからも変わっていくはず。今後どのように進化していくのか、引き続き注目していきたいと思います。
今日もお読みいただきありがとうございます。
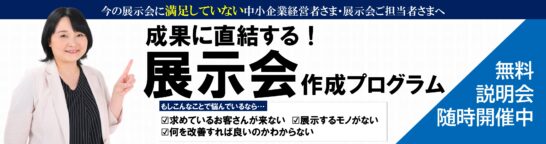
中小企業向け展示会サポートプログラムのご案内。無料説明会随時受付中!
>>展示会活用アドバイザー大島節子へのお仕事依頼はこちらからお願いします