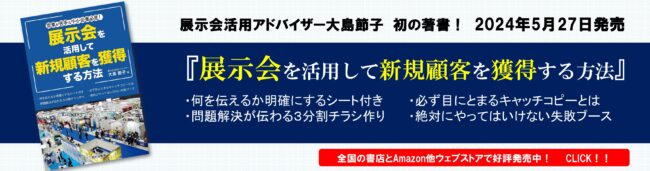生成AI時代のサイト集客「LLMO」とは?
おはようございます^^
自社の問題解決力を見える化し展示会を成功に導く、展示会活用アドバイザーの大島節子です。
昨日の大阪は今年一番の暑さだったのですね。できる対策をしていかないと。そんな早朝の大阪から今朝も展活タイムズをお届けします。
無視できない新しいサイト流入経路
皆さんは最近「LLMO」という言葉を耳にしたことはありますか?
LLMOとは、Large Language Model Optimization(大規模言語モデル最適化)の略。 要は、ChatGPTのような生成AIに、自社のサイトを“引用元”として認識してもらい、ユーザーへの回答にうまく使ってもらうための対策、ということです。
正直なところ私も「まだ先の話かな」と思っていました。 しかし先日ふと自分の展活サイトのアクセス解析を見て、その考えは変わりました。今日はその実例と、私たちがこれからLLMOとどう向き合っていくべきかについて、考えてみたいと思います。

【実例】AIから展活サイトへの訪問者
まずはこちらのデータをご覧ください。 過去1年間の展活サイトへのアクセス元を調べてみたところ、下記のようなAIからの流入が確認できたのです。
- ChatGPT:46件
- perplexity:27件
- gemini:7件
- felo:6件
- copilot:5件
全体のアクセス数は3万なのでGoogle検索などと比べれば、まだまだ、ごくごく一部の数字です。 でも数年前には存在しなかった新しいアクセス経路が、確かに生まれているということは紛れもない事実。 これはもう無視できない時代の変化だと感じます。
「LLMO」と、これまでの「SEO」は何が違うのか?
ではSEOとの違いと関係性について、私なりに整理してみます。
- SEO(検索エンジン最適化): Googleなどの検索結果で、自社のサイトを「上位に表示させる」ための対策。
- LLMO(大規模言語モデル最適化): 生成AIがユーザーの質問に答える際に、自社のサイト情報を「信頼できる情報源として引用・参照してもらう」ための対策。
つまり、LLMOはSEOと対立するものではなく、これからの時代、両方に取り組んでいく必要がある、車の両輪のような関係になっていくのだと思うのです。
では、私たちは何をすればいい?
専門家ではない私たちが、まず何から始めればいいのでしょうか? 5月にマイドームおおさかで開催されたマーケティングテクノロジーフェア大阪で講演された元Googleで日本経済大学教授の金谷さんのお話(その時の記事はこちら)を受けて。そして色々と調べていく中で、特別な対策というよりも、むしろ私たちがこれまで大切にしてきたことの延長線上にあるように思うのです。今日からでも意識できる、基本的な考え方を3つご紹介します。
①「一次情報」と「専門性」を突き詰める
AIが最も参考にし価値を置くのは、他サイトの情報の受け売りではない自身の経験や独自のデータ、専門知識に基づいた「一次情報」です。自社の強みやお客様から直接聞いた「生の声」、長年の経験から得たノウハウこそが最高のLLMO対策になります。
②「Q&A」形式で、分かりやすく書く
AIはユーザーの「質問」に「回答」を生成します。ならば、私たちのサイトもお客様が抱えるであろう具体的な質問に対し、明確に回答するような構成で記事を書くことが有効です。専門用語を並べるだけでなく「つまり、こういうことです」と分かりやすく解説してあげる親切さが、AIにも、もちろん人間にも評価されます。
③「何者か」を明確にする
「この記事は、〇〇の専門家である△△が、□□という経験に基づいて書いています」というように、情報の信頼性を示す「運営者情報」や「監修者プロフィール」をしっかり記載すること。AIに「この記事は信頼できる情報源だ」と認識してもらう上で今後ますます重要になるでしょう。
結局のところこれらは全て検索エンジンのためでもAIのためでもなく「読んでくれる人のために本当に価値ある情報を分かりやすく誠実に届けよう」という想い。商売や情報発信の“本質”と同じなんですよね。
まとめ:まずはその存在に気づくことから
「LLMO」という新しい潮流はもう始まっています。 現時点でのアクセス数はまだ僅かかもしれません。しかし数年後にはこれが大きな流れになっている可能性も十分にあります。
まずは自社のサイトに「AIからのアクセス」という新しいお客様が来始めているかもしれない、という事実に気づきアンテナを張っておくこと。 そしてこれまで通り、いえこれまで以上に「読んでくれる人のために」価値ある情報を発信し続けること。
それが変化の時代に適応していくための、最も大切で確実な第一歩なのだと私は思います。
今日もお読みいただきありがとうございます。
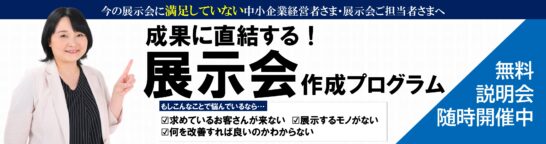
中小企業向け展示会サポートプログラムのご案内。無料説明会随時受付中!
>>展示会活用アドバイザー大島節子へのお仕事依頼はこちらからお願いします