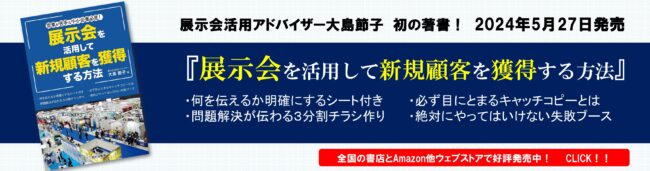刈谷商工会議所メッセナゴヤ2025共同出展個別相談会
おはようございます^^
自社の問題解決力を見える化し展示会を成功に導く、展示会活用アドバイザーの大島節子です。
昨晩の皆既月食、大阪からも見えたようですね。そんな早朝の大阪から今朝も展活タイムズをお届けします。
90分で乗り越えた事例集
9月4日と5日の2日間にわたり、刈谷商工会議所にてメッセナゴヤ2025に共同出展される企業8社との個別相談会を実施しました。1社90分、合計12時間にもおよぶセッション。各社の想いに触れる中で多くの出展者が共通して直面する「3つの壁」が見えてきました。
「うちの技術はすごいのに、良さが伝わらない…」 「たくさんのブースに埋もれて、素通りされてしまう…」 「名刺は集まるのに、なぜか成果に繋がらない…」
この記事では、そんなお悩みを解決するための具体的なヒントを、相談会で生まれたリアルな事例と共にご紹介します。

【第1の壁:伝わらない】〜来場者の自分ごとに出来ていますか?〜
多くの企業が最初にぶつかるのが、この「伝わらない」という壁です。優れた技術や製品があるにも関わらず、その価値が来場者に届いていないケースは少なくありません。
解決の鍵は「自分たちが言いたいこと」から「来場者が解決したい課題」へ視点を転換することです。
<Case 1:メッセージの解像度を上げたB社>
昨年「環境配慮」という大きなテーマを掲げたものの、メッセージが抽象的で来場者の関心を惹ききれなかったと反省されていたB社。今年はより具体的で切実な課題に寄り添うコンセプトへと舵を切りました。ターゲットが思わず「うちのことだ」と感じるメッセージで、ブースへの引き込みを狙います。
<Case 2:キャッチコピーを21案洗い出したA社>
すでに完成度の高いチラシを準備されていた技術メーカーのA社。しかし、企業の本当の強みを対象者に突き刺すため、最も重要なキャッチコピーを徹底的に見直しました。生成AI(Gemini)も壁打ち相手にしながら合計21案ものキャッチコピーを洗い出し、訴求力を最大化する一本を練り上げました。
【第2の壁:素通りされる】〜見込み客が確実に止まるブースとは?〜
次に立ちはだかるのが、数多のブースの中に埋もれてしまう「素通りされる」壁です。来場者の足を止め自社の空間に引き込むためには改善が必要です。
<Case 3:「引き算のブース設計」で洗練させたD社>
すでにメディアでも有名な人気商品をお持ちのD社。これまでのブースは伝えたい情報が多く、少し雑然とした印象でした。そこで今回は、リニューアルしたチラシのコンセプトに合わせ、掲示物をあえて絞り込み、洗練されたタペストリーを主役にした「引き算のブース設計」をご提案。ブースがすっきりしたことで、設営・撤収の効率が上がるという副次的な効果も大変喜んでいただけました。
<Case 4:「主役」を明確にしたG社>
本業であるBtoBの部品加工をPRしたいのに、どうしてもBtoCの製品に注目が集まってしまう、というモヤモヤを抱えていたG社。来場者の動線を考えブースの一番手前に本業の技術サンプルを、奥にBtoC製品を配置することで展示の「主役」と「脇役」を明確にするレイアウトを固めました。
【第3の壁:やりっぱなし】〜名刺を「未来の売上」に変える仕組み〜
そして最も“もったいない”のがこの「やりっぱなし」の壁です。会期中は多くの名刺交換ができても、その後のフォローが続かず、成果に繋がらないケースです。
解決の鍵は、会期中の「記録」を標準化し、会期後の「行動」をスムーズにすることです。
<Case 5:300枚の名刺を活かす仕組みを導入したF社>
昨年の初出展でなんと300件もの名刺交換があったにも関わらず、一切アフターフォローをしなかったというF社。それでも複数社から見積依頼があったというのですから、そのポテンシャルは計り知れません。今年はこの機会損失をなくすため「接客内容記録シート」を導入。ヒアリング内容や相手の熱量をその場で記録し、見込み客情報を成果へ繋げる仕組みを提案しました。
【補足】 この「接客内容記録シート」は、多くの企業が導入を決められた便利なツールです。担当者によってヒアリング内容や記録にバラつきが出てしまうのを防ぎ、会期後に「誰に」「いつ」「何を」連絡すべきか、的確なフォローアップを行うための材料になります。展示会での出会いを「点」で終わらせず「線」として育てるための第一歩です。
まとめ
相談会を終えた後、ご参加いただいた8社の皆さんの表情は漠然とした不安から「やるべきことが見えた」というスッキリした顔へと変わっていました。
- 誰のどんな課題を解決できるのか?(コンセプトの明確化)
- どうすれば足を止め、心を動かせるか?(効果的なブース設計)
- どうすれば出会いを成果に変えられるか?(アフターフォローの仕組み化)
この3つのポイントを事前に準備することが、展示会成功の鍵ですね。メッセナゴヤ2025本番で、各社が望む成果を上げられることを、心から応援しています。
今日もお読みいただきありがとうございます。
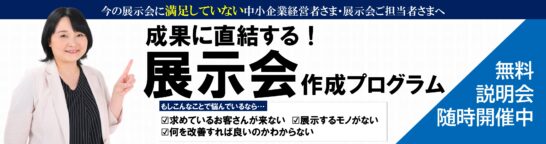
中小企業向け展示会サポートプログラムのご案内。無料説明会随時受付中!
>>展示会活用アドバイザー大島節子へのお仕事依頼はこちらからお願いします