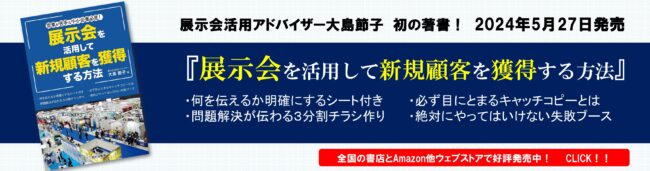コンパニオンが消えた?モビリティーショーの変化
おはようございます^^
自社の問題解決力を見える化し展示会を成功に導く、展示会活用アドバイザーの大島節子です。
乾燥してますねぇ。あんなにも蒸し蒸ししてたのに…。そんな早朝の大阪から今朝も展活タイムズをお届けします。
“ハイヒールとミニスカート”が減った理由
先日、11月9日(日)までの11日間にわたって開催されたジャパンモビリティショー2025。2年に1度の、クルマと未来のモビリティの祭典です。
その会期中、X(旧Twitter)上で、ある投稿が話題になっているのを目にしました。 「今年のモビリティショー、コンパニオンがほぼゼロだった」と。「本当だろうか?」と私自身も調べてみたところ、「ゼロは言い過ぎ。今もいらっしゃるには全然いらっしゃる」というのが実情のようです。
しかし明らかに変わったことがあるようです。 それは、ブースに立つ女性たちの「衣装」と、そして何より「役割」です。この変化は日本の展示会が、そして日本を代表する自動車産業が、大きな転換点を迎えていることを示しています。
変わったのは「役割」。“見せる”から“伝える”プロへ
Xで話題になった「コンパニオンが減った」という印象の正体。それは肌の露出を抑えたプロフェッショナルな制服をまとい、身体で注目を集めるスタイルから「説明員」や「MC」としての能力を重視するスタイルへと、彼女たちの役割が明確にシフトしたことです。
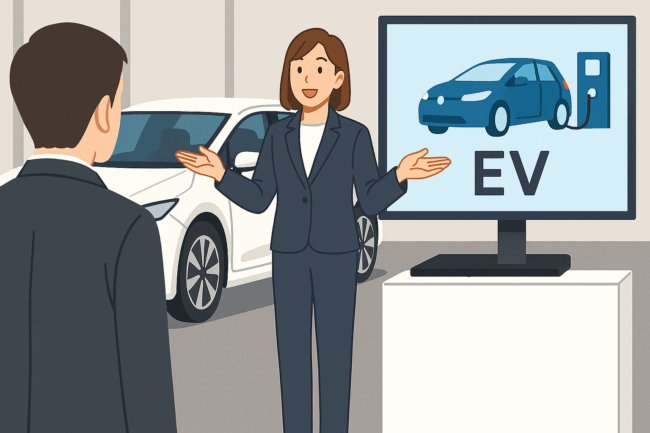
この変化は、ブースに立つ彼女たち自身のキャリアにとっても、非常にポジティブなことだと私は思います。
「カメラ小僧」と呼ばれる人々の撮影対象になることで得られる注目は、悲しいかな、若い時期の数年で終わってしまいます。しかし自分の言葉で製品の魅力や未来のビジョンを理路整然とプレゼンテーションする「MC」としての能力は、一生モノの専門スキルとなります。彼女たちは「モノの隣に立つ飾り」ではなく、企業の顔として最前線で「対話する」プロフェッショナルへと進化したのです。
なぜ、この変化が起きたのか?
ではなぜこの変化は起きたのでしょうか。背景には、無視できない3つの要因があります。
要因①:欧米の“世界標準”
そもそも欧米の国際格式オートショーでは、「コンパニオン」という存在は、もっと以前から(ほぼ)存在しなかったと言われています。男女平等が強く叫ばれる社会において、「女性の身体」を「車の横に添える“モノ”」として扱うことへの強い拒否感があるためです。
要因②:日本産業界の“危機感”
日本を代表する自動車業界が、いつまでも「一部の男性の性的な視線」を優先するような展示を続けていればどうなるか。「あの国の産業は、まだそんなレベルなのか」と、世界から“時代遅れ”のレッテルを貼られてしまいます。グローバルで戦う企業にとって、このブランディングの毀損は致命的です。
要因③:製品自体の“変化”
そしてこれが展活的に最も重要なポイントです。「東京モーターショー」から「ジャパンモビリティショー」へと名称が変わったように、展示されるものが「カッコいい車(=モノ)」から「複雑なモビリティ・ソリューション(=コト)」に変わりました。
EV、自動運転、社会インフラとしての活用…。これらの複雑な概念は、ただ立っているだけでは伝わりません。来場者の疑問に的確に答え、未来の可能性を語り合う「対話」と「説明」が不可欠であり、その役割を担うプロフェッショナルな説明員が求められるのは、必然なのです。
「華やかさ」の尺度が変わった
「じゃあ、展示会から“華”がなくなって寂しい」と思う方もいるかもしれません。 しかし、それは違います。「華やかさ」の尺度が、変わったのです。
東南アジアなどのオートショーでは、今も露出の高いコンパニオンが溢れていると聞きます。これはその国における「車の貴重性」や「女性の社会進出度」と深く関連しているように思えます。
日本の展示会におけるこれからの「華」とは、肌の露出度や、カメラのフラッシュの量ではありません。
来場者の「知りたい!」という純粋な好奇心と、出展者の「伝えたい!」という情熱がぶつかり合い、活発な“対話”が生まれている知的興奮の光景こそが、これからの展示会が目指すべき、真の「華やかさ」ではないでしょうか。
まとめ:“撮る”展示会から、“話す”展示会へ
ジャパンモビリティショーで見られたこの変化は、日本の展示会全体が「一方的に見せる(撮らせる)場」から、「双方向で対話する(課題解決する)場」へと、ようやく成熟しつつある喜ばしい証拠です。
展示会は、あなたの会社の“本気度”と“未来へのビジョン”を伝える場所。 「カメラ小僧」ではなく「未来のお客様」と真剣に向き合う。この当たり前のことが日本の展示会でもスタンダードになり始めたのだと、非常にポジティブな変化だと思うのです。
今日もお読みいただきありがとうございます。
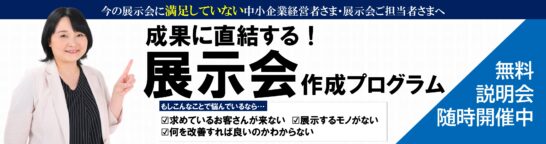
中小企業向け展示会サポートプログラムのご案内。無料説明会随時受付中!
>>展示会活用アドバイザー大島節子へのお仕事依頼はこちらからお願いします